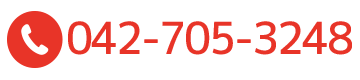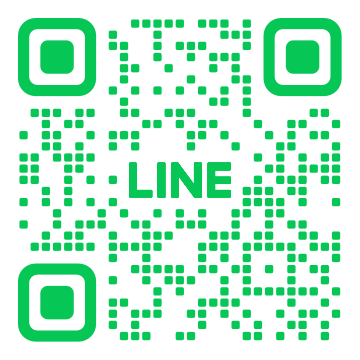喘息とは?
喘息とは?
喘息(ぜんそく)は、気道(空気の通り道)が慢性的に炎症を起こし、発作的に狭くなる病気です。これにより呼吸がしづらくなり、咳や息苦しさ、喘鳴(ゼーゼー・ヒューヒューという音)が発生します。小児から成人まで幅広い年齢層で発症し、適切な治療と生活管理が重要です。
発症年齢は、幼児期と40~60歳代の2つの時期に発症しやすい病気です。子どもの喘息は思春期に改善することが多いですが、約30%は大人になっても続くとされています。また、大人になってから発症する「成人喘息」は40~60歳代が多く、全体の半数以上を占めます。
症状の重さは人それぞれで、軽い咳程度のものから、適切な治療をしないと命に関わる重症の発作まであります。治療法は発作の頻度や強さによって異なり、軽症の場合は気管支拡張薬を使用し、頻繁に発作が起こる場合や、夜間の睡眠中にもしばしば発作が生じるようであれば、ステロイドなどの治療薬を使うこともあります。

喘息の原因
喘息の原因
喘息の原因は複数ありますが、主に以下の要因が関係しています。
•アレルギー・・・ダニ、ハウスダスト、花粉、ペットの毛など。
•環境要因・・・大気汚染、タバコの煙、気温や湿度の変化。
•運動やストレス・・・激しい運動や強いストレスが発作を引き起こすことがあります。
•感染症・・・風邪やインフルエンザなどのウイルス感染。
•遺伝的要因・・・家族に喘息の人がいる場合、発症リスクが高くなります。
喘息の主な症状
喘息の症状は個人によって異なりますが、以下のようなものが一般的です。
•咳が続く (特に夜間や早朝に悪化することが多い)
•息苦しさ (特に運動時や夜間)
•喘鳴 (ゼーゼー・ヒューヒューする呼吸音)
•胸の圧迫感
•発作的に症状が悪化し、呼吸困難になることがある
日常生活での注意点
1. 環境を整える
•部屋を清潔に保ち、ダニやハウスダストを減らす。
•加湿器や空気清浄機を活用し、空気の質を改善する。
•タバコの煙や香水など、刺激となるものを避ける。
2. 適切な治療を継続する
•医師の指示に従い、吸入薬や内服薬を正しく使用する。
•症状が軽い時でも自己判断で治療をやめず、継続する。
•定期的に医師の診察を受ける。
3. 運動やストレス管理
•激しい運動を避け、適度な運動を心がける。
•ストレスをためないようにリラックスする時間を確保する。
•ヨガや深呼吸を取り入れ、呼吸を整える習慣をつける。
4. 発作時の対応を知る
•発作が起きたときの対応方法を事前に確認しておく。
•発作時に使用する薬(リリーバー)を常備する。
•症状が悪化した場合は、迷わず医療機関を受診する。
喘息は適切な管理と治療を行うことで、症状をコントロールしながら日常生活を快適に過ごすことができます。環境を整え、医師の指示に従いながら、上手に付き合っていくことが大切です。気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
喘息に対する東洋医学の考え方
東洋医学では、喘息は「哮喘(こうぜん)」と呼ばれ、主に肺・脾・腎の機能低下や気血(きけつ)の滞りが原因と考えられています。喘息の発作を一時的な症状として捉えるのではなく、体全体のバランスの乱れとして捉え、根本的な体質改善を目指すことが特徴です。
<喘息の主な原因(東洋医学の視点)>
東洋医学では、喘息は以下のような原因によって引き起こされると考えられています。
① 肺の虚弱(肺気虚・肺陰虚)
肺は「気(エネルギー)」を全身に巡らせ、呼吸をコントロールする重要な臓器です。肺の機能が弱まると、外邪(外部からの病気の原因となるもの)に対する抵抗力が低下し、喘息を引き起こしやすくなります。
• 肺気虚(はいききょ)・・・息切れ、倦怠感、風邪をひきやすい
• 肺陰虚(はいいんきょ)・・・乾いた咳、のどの渇き、口が乾く
② 痰湿(たんしつ)の滞り
「湿(しつ)」は水分代謝の乱れを意味し、「痰湿」となると体内に不要な水分が溜まり、気道を塞ぐ原因になります。特に、胃腸(脾)の機能が弱いと痰がたまりやすくなり、喘息の発作を引き起こすことがあります。
• 症状・・・痰が多く、ゼーゼー・ヒューヒューする、胸が重く苦しい
③ 腎の機能低下(腎虚)
東洋医学では、「腎」は生命エネルギー(精)を蓄え、呼吸を深く安定させる役割を持つと考えられています。腎が弱ると呼吸が浅くなり、発作が起きやすくなります。特に、先天的に体が弱い子どもや、高齢者の喘息に関連が深いとされています。
• 症状・・・長引く喘息、冷え、足腰のだるさ、夜間の発作
鍼灸と喘息
鍼灸が喘息に効果があるとされる理由はいくつかあります。以下のメカニズムによって、喘息症状の緩和や発作の予防が期待できます。
1. 自律神経の調整
鍼灸は自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスを整える働きがあります。交感神経は気管を拡張させて、副交感神経は気管を収縮させます。喘息は、副交感神経の過剰な興奮によって気道が収縮し狭くなりやすくなることが一因とされています。また夜間は副交感神経が優位になるため、気道が狭くなり、喘息発作が起こりやすくなります。
鍼灸によって交感神経と副交感神経のバランスが整うことで、気道の過剰な収縮を抑える効果があります。
2. 免疫機能の向上と抗炎症作用
喘息は気道の慢性的な炎症が原因の一つです。鍼灸は体の免疫機能を調整し、炎症を抑える作用があるとされています。特に、「肺」や「脾」、「腎」に関わるツボを刺激することで、免疫系の過剰な反応を抑え、気道の炎症を軽減する効果があります。
3. 呼吸機能の改善
鍼灸によるツボ刺激は、呼吸筋(横隔膜や肋間筋)の緊張を和らげ、スムーズな呼吸を促します。また特定のツボを刺激することで、肺の機能を高め、呼吸がしやすくなる効果につながります。
4. ストレスの軽減
ストレスは喘息発作の誘因の一つです。鍼灸にはリラクゼーション効果があり、ストレスを軽減することで喘息発作の予防につながります。特定のツボの刺激がリラックス効果をもたらします。
5. 体質改善による予防効果
東洋医学では、喘息は「肺の虚弱」や「気の滞り」などが原因と考えられます。鍼灸治療によって体全体の気血の流れを改善し、根本的な体質改善を図ることで、喘息の発作を起こしにくい体に導くことができます。
鍼灸は自律神経の調整、炎症の軽減、呼吸機能の改善、ストレス緩和、体質改善などを通じて喘息の症状を緩和する効果があります。また食事療法、生活習慣の改善を組み合わせることで、健康で快適な生活を送れる状態へ導くことができます。
喘息を根本から改善したい場合は、東洋医学的なアプローチを取り入れつつ、西洋医学の治療と併用するのがおすすめです。