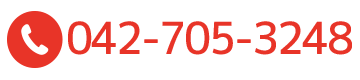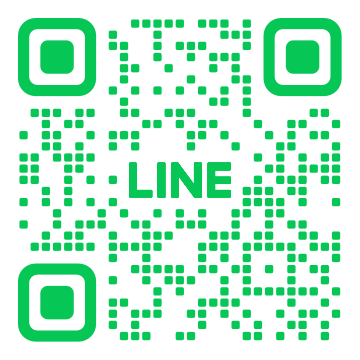逆流性食道炎について
逆流性食道炎について
逆流性食道炎は、胃から食道へ胃酸や消化物が逆流し、食道の粘膜が炎症を起こす病気です。近年は食生活の欧米化やストレス、肥満などにより増加傾向にあります。

主な原因
主な原因
●胃酸の逆流 ・・・ 下部食道括約筋(胃と食道の境目の筋肉)の働きが弱まると、胃酸が逆流しやすくなります。
●生活習慣 ・・・ 脂っこい食事、アルコール、喫煙、過食、早食いなど。
●加齢 ・・・ 筋肉の衰えや内臓の位置変化も影響します。
●姿勢や体型 ・・・ 猫背、肥満、妊娠中もリスク要因となります。
主な症状
●胸やけ(胸の奥が熱くなるような感覚)
●酸っぱい液が口まで上がってくる感じ(呑酸)
●のどの違和感や声のかすれ
●慢性的な咳や喘鳴
●胃もたれや食欲不振
症状が長引くと、食道潰瘍やバレット食道など合併症を招く恐れがあります。
特 徴
逆流性食道炎は、食後や横になったときに症状が強く出やすいのが特徴です。特に夜間の就寝中に悪化する方が多く、睡眠の質を下げ、日常生活にも影響します。
日常生活での注意点
•食べ過ぎを避け、腹八分目を心がける
•脂っこいもの・甘いもの・アルコール・カフェインを控える
•食後すぐに横にならない(2〜3時間は間をあける)
•寝るときは上半身を少し高くする
•便秘や肥満を予防する
•ストレスをため込まず、規則正しい生活を送る
東洋医学の考え方
東洋医学では、逆流性食道炎は「胃気の上逆(胃のエネルギーが上へ逆流する)」と捉えます。胃や脾(消化器系)の働きが弱り、気や血の巡りが滞ると、胸やけや呑酸といった症状が現れるのです。
鍼灸では、胃腸の働きを整えるツボ、自律神経のバランスを調えるツボを用い、消化機能を高め、胃酸の逆流を抑える体質改善を目指します。また、ストレスや冷えからくる症状にもアプローチし、再発しにくい体へ導きます。
逆流性食道炎と鍼灸
逆流性食道炎は、胃酸そのものの問題だけでなく、胃腸の働き・自律神経の乱れ・ストレス・体質が大きく関わっています。鍼灸はこれらに総合的に働きかけることで、自然治癒力を引き出し、症状を改善へと導きます。
1. 胃腸の機能を整える
鍼灸で胃腸のツボを用いることで、胃の働きを正常化し、消化を助けます。これにより、胃酸の過剰分泌や逆流を抑えやすくなります。
2. 自律神経のバランスを調える
逆流性食道炎は、自律神経の乱れによって下部食道括約筋が緩むことで悪化する場合があります。鍼灸は副交感神経を優位にし、食道の働きを整えて逆流を防ぎます。
3. ストレスを軽減する
ストレスは胃酸の分泌を促進し、逆流の大きな原因になります。鍼灸は心身をリラックスさせる作用があり、精神的な緊張を和らげることで症状の改善につながります。
4. 冷えや体質を改善する
東洋医学では「脾胃の弱り」 「気の停滞」 「冷え」が逆流を引き起こす要因と考えます。鍼灸は全身の血流を改善し、体質そのものを整えることで再発防止に役立ちます。
まとめ
鍼灸は逆流性食道炎の根本原因である 胃腸機能の低下・自律神経の乱れ・ストレス・体質の弱り にアプローチし、薬に頼らず自然に回復しやすい体をつくるサポートをします。
当院での施術の流れ
当院ではまず丁寧なカウンセリングを行い、症状や生活習慣を詳しくお伺いします。そのうえで、体質や自律神経の状態に合わせた鍼灸施術を行い、胃腸の働きを整えていきます。施術後は生活習慣のアドバイスも行い、日常からの改善をサポートします。
こんな方におすすめです
•薬を飲んでもなかなか症状が改善しない方
•胸やけや喉の違和感で毎日つらい思いをしている方
•夜眠るときに逆流が気になって熟睡できない方
•ストレスや疲労で胃腸の調子が崩れやすい方
•根本から体質を改善して、再発を防ぎたい方