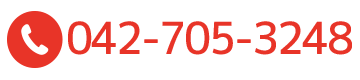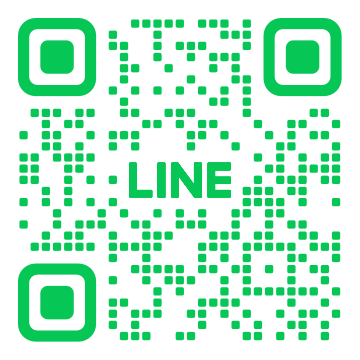胃腸炎
胃腸炎
胃腸炎は、ウイルスや細菌、または生活習慣などによって胃や腸に炎症が起こる病気です。急性のものは数日で治ることが多いですが、強い症状が出る場合や慢性化することもあるため、注意が必要です。

主な原因
主な原因
感染性:ノロウイルスやロタウイルス、サルモネラ菌、大腸菌などの感染が代表的です。
非感染性:暴飲暴食、過度の飲酒、薬の副作用、ストレスなどでも起こります。
主な症状
●吐き気・嘔吐
●下痢
●腹痛や下腹部の不快感
●発熱、全身のだるさ
●脱水症状(重症の場合)
症状の強さは原因や体力によって異なります。
特 徴
感染性胃腸炎は冬場に多く発生し、家族や集団で広がりやすいのが特徴です。非感染性の胃腸炎は、疲れやストレスで免疫が落ちたときや、食べ過ぎ・飲み過ぎで起こることがあります。
日常生活での注意点
●水分補給をしっかり行う(経口補水液などがおすすめ)
●消化に良い食事を心がける(おかゆ、うどん、バナナなど)
●十分な休養をとる
●感染予防として手洗い・うがいを徹底する
●症状が重いときや長引く場合は医療機関の受診が必要です。
胃腸炎の西洋医学での治療法
胃腸炎の治療は、原因(ウイルス・細菌・生活習慣など)や症状の重さによって異なります。基本的には 症状を和らげ、水分と栄養を補いながら自然回復を待つことが中心となります。
◆ 対症療法
•水分補給・・・脱水を防ぐため、経口補水液などで水分・電解質を補います。
•整腸剤・止瀉薬・・・下痢や腹痛が強い場合に使用されます。
•制吐薬・・・吐き気や嘔吐を和らげるために処方されることがあります。
•解熱鎮痛薬・・・発熱や全身のだるさを改善する目的で使用されることがあります。
◆ 抗菌薬
細菌性胃腸炎(サルモネラ菌、大腸菌、カンピロバクターなど)が疑われる場合には抗生物質が用いられることもあります。ただし、ウイルス性胃腸炎には効果がありません。
◆ 食事療法
症状が落ち着くまでは消化にやさしい食事(おかゆ、バナナ、うどんなど)を少量ずつ摂ることが推奨されます。油っこいものや刺激物、アルコールは避けます。
◆ 休養
十分な睡眠と安静をとることが、回復を早める大切な要素です。
東洋医学の考え方
東洋医学では、胃腸炎は「脾胃(ひい)の弱り」や「外邪(細菌やウイルス)」によるものと考えます。特に、冷えや湿気、過度な飲食が胃腸に負担をかけ、「気・血・水」の巡りが乱れることで症状が現れます。
鍼灸では、脾胃を整え、消化機能を高めるツボや、体の防御力(正気)を高める施術を行います。これにより、症状を和らげるとともに、胃腸が弱りやすい体質の改善にもつながります。
胃腸炎と鍼灸
胃腸炎は、感染や暴飲暴食、ストレスなどによって胃腸に負担がかかり、消化吸収の働きが弱って起こります。鍼灸は、症状を和らげるだけでなく、胃腸の働きを整え、再発しにくい体づくりをサポートします。
◆ 胃腸の機能を整える
鍼灸は「脾胃(消化器系)」の働きを高める効果があります。胃腸の動きを助けることで、吐き気・下痢・腹痛などの不快な症状をやわらげます。
◆ 自律神経のバランスを整える
胃腸は自律神経の影響を強く受けます。鍼灸は交感神経・副交感神経のバランスを整え、ストレス性の胃腸炎や、緊張からくる消化不良の改善に役立ちます。
◆ 免疫力を高める
東洋医学では、胃腸炎は「正気(体を守る力)」が弱っているときに起こりやすいとされます。鍼灸は体の免疫機能を高め、細菌やウイルスに負けにくい体を作ります。
◆ 冷えと湿気を取り除く
お灸やツボ刺激によって体を温め、胃腸にたまりやすい「冷え」や「湿」を取り除きます。これにより、腹部の冷えからくる下痢や痛みを改善します。
◆ 再発予防と体質改善
鍼灸は一時的な症状の緩和だけでなく、胃腸が弱りやすい体質そのものを整えることができます。繰り返し起こる胃腸炎の予防や、慢性的な胃腸不調にも効果的です。