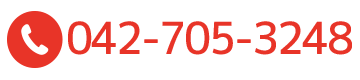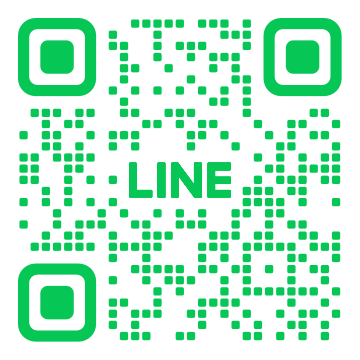顔面けいれん(顔面痙攣)について
顔面けいれん(顔面痙攣)について
顔面痙攣は、目の周りや口元が自分の意思とは関係なくピクピクと動いてしまう症状です。最初は片方の目の周りから始まり、徐々に口元や頬へと広がることが多く、症状が進行すると会話や食事に支障をきたすこともあります。頻度は、最初は緊張したときなど時々症状が現れますが、徐々にけいれんしている時間が長くなっていきます。やがて一日中、ときには寝ていても起こるようになることあります。

このような症状でお悩みではありませんか?
このような症状でお悩みではありませんか?
✅ 目の周りがピクピクと勝手に動く
✅ 片側の顔が不規則に引きつる
✅ 緊張すると症状が悪化する
✅ まばたきが増え、目の開けづらさを感じる
顔面痙攣は放っておくと悪化することもあるため、早めの対処が大切です。
顔面痙攣の原因
顔面痙攣の主な原因は、顔の筋肉を動かす「顔面神経」が何らかの影響を受けることによって引き起こされます。
1. 脳の血管による圧迫(最も多い原因)
脳の血管が顔面神経を圧迫し、神経が刺激されることで顔の筋肉が勝手に動いてしまいます。特にストレスや疲労が重なると悪化しやすい傾向があります。
2. 顔面神経の損傷や異常
顔面神経麻痺(ベル麻痺)を経験した後に、神経が回復する過程で異常な信号が送られることがあります。
3. ストレスや疲労の影響
精神的なストレスや睡眠不足、長時間のパソコン作業などによって、顔の筋肉が過剰に緊張し、痙攣が起こりやすくなります。
4. 眼精疲労やドライアイ
目の酷使により、まばたきの回数が増え、目の周りの筋肉が疲労することで、痙攣が誘発されることがあります。
顔面痙攣の特徴と症状
✅ 最初は目の周りに症状が出る(片側のまぶたがピクピクする)
✅ 進行すると頬や口元にも広がる(口角が引きつる、顔の片側がピクッと動く)
✅ ストレスや疲労で悪化しやすい
✅ 眠っている間は症状が出ないことが多い
片側だけに症状が出るのが特徴ですが、両側に現れる場合は他の病気が隠れていることもあるため、注意が必要です。
日常生活での注意点
顔面痙攣を悪化させないためには、神経の興奮を抑え、血流を良くすることが大切です。
1. ストレスを溜めない
長時間のパソコン作業やスマホの使用は、目の疲れやストレスを引き起こしやすいため、適度に休憩を取ることが大切です。
2. 良質な睡眠をとる
睡眠不足は神経の過敏性を高めるため、7~8時間の睡眠を意識しましょう。
3. 目を温めてリラックス
ホットタオルを目の上にのせることで、目の周りの筋肉の緊張を和らげ、痙攣を抑える効果が期待できます。
4. カフェインやアルコールを控える
神経を興奮させるカフェインやアルコールの摂取を控え、リラックスできるハーブティーなどを取り入れるのもおすすめです。
西洋医学での治療法
顔面痙攣の治療は、症状の重さや原因に応じて 薬物療法・ボツリヌス療法・手術 などが選択されます。
1. 薬物療法(軽症~中等症向け)
神経の興奮を抑える薬を使用し、症状を和らげます。
🔹 主に使われる薬
✅ 抗けいれん薬(カルバマゼピン、バルプロ酸)
➡ 神経の異常な興奮を抑える。
✅ 筋弛緩薬(エペリゾンなど)
➡ 筋肉の緊張を和らげる。
✅ 精神安定剤・抗不安薬(ジアゼパムなど)
➡ ストレスによる悪化を防ぐ。
▶ 効果・・・軽症の場合は症状が和らぐことがある。
▶ デメリット・・・効果に個人差があり、副作用(眠気・ふらつき)が出ることも。
2. ボツリヌス療法(ボトックス注射)
現在最も一般的な治療法で、顔面痙攣の治療の第一選択肢となることが多い。
🔹 治療の流れ
1. ボツリヌストキシン(ボトックス)を顔面の筋肉に注射
2. 神経から筋肉への信号をブロックし、痙攣を抑える
3. 約3~6か月効果が持続するため、定期的な注射が必要
▶ 効果・・・高確率で症状が改善する。
▶ デメリット・・・数ヶ月ごとに注射が必要、効果が切れると再発。
3. 手術(血管による神経圧迫が原因の場合)
薬やボツリヌス療法で改善しない場合、外科手術が検討される。
🔹 代表的な手術
✅ 微小血管減圧術(MVD手術)
➡ 顔面神経を圧迫している血管を移動させることで、根本的に治療。
➡ 成功率が高く、約80~90%の患者で改善が見られる。
▶ 効果・・・根本的に治療できる可能性がある。
▶ デメリット・・・全身麻酔が必要で、稀に合併症(聴力低下・顔面麻痺)が起こることも。
顔面痙攣の治療は、症状の程度やライフスタイルに応じて選択されます。
まずは専門医に相談し、自分に合った治療法を見つけることが大切です。
東洋医学における顔面痙攣の考え方
東洋医学では、顔面痙攣は「気血(きけつ)の滞り」や「肝の不調」が原因と考えます。
1.気血の滞り(気滞・瘀血)
気や血の流れが悪くなると、顔面神経が正常に働かず、痙攣が起こりやすくなります。これは、ストレスや疲労、血流の悪さが影響していると考えられます。
🔹改善方法
•ストレッチや軽い運動で巡りを良くする
2.肝の不調(肝風内動)
東洋医学では、「肝」は神経系や筋肉の動きと深く関係しているとされ、肝のバランスが崩れると顔面痙攣が起こると考えます。特に、ストレスが多いと「肝気鬱結(かんきうっけつ)」といって、気の流れが滞りやすくなります。
🔹改善方法
•リラックスする時間を作る(深呼吸、瞑想など)
•自律神経を整える食事(温かい食事、発酵食品を摂る)
顔面痙攣は、顔面神経への圧迫やストレス、疲労などが原因で起こります。西洋医学ではボツリヌス療法や薬物療法が用いられますが、東洋医学では気血の流れを整え、ストレスを減らすことで改善を目指します。
🔹改善のポイント
✅ 目の疲れをとる(ホットタオル、目のマッサージ)
✅ ストレスを溜めない(リラックス時間を作る)
✅ 血流を良くする(鍼灸、ツボ押し、運動)
✅ 良質な睡眠をとる
症状が続く場合は、鍼灸や漢方を取り入れながら、無理せずリラックスできる環境を整えることが大切です。
顔面痙攣と鍼灸治療
鍼灸は、顔面痙攣の原因となる 神経の興奮を鎮め、血流を改善し、筋肉の緊張を和らげる ことで症状の軽減を目指します。
1. 顔面神経のバランスを整える
顔面痙攣は、顔面神経が過剰に興奮し、筋肉が無意識に収縮することで起こります。鍼灸は、神経の働きを調整し、異常な神経信号を和らげる作用が期待できます。
🔹 効果のポイント
✅ 鍼刺激によって神経の興奮を抑える
✅ 筋肉の過緊張をほぐし、痙攣を軽減する
✅ 自律神経のバランスを整え、症状の悪化を防ぐ
特に、顔面神経が圧迫されている場合、周囲の血流を改善し、神経の働きを正常化することが重要です。
2. 血流を促進し、神経や筋肉の働きを回復
東洋医学では、「気血(きけつ)」の巡りが悪くなると、神経や筋肉の動きが乱れると考えられています。鍼灸は、血流を改善し、神経や筋肉の回復を助ける効果があります。
🔹 改善が期待できるポイント
✅ 血行を促進し、神経細胞の回復をサポート
✅ 栄養と酸素を神経や筋肉に届け、痙攣を鎮める
✅ 代謝を促し、炎症を抑える
3. ストレスや自律神経の乱れを整える
顔面痙攣は ストレスや疲労、睡眠不足 によって悪化しやすいです。これは、自律神経の乱れが原因となり、神経の過剰な興奮を引き起こしているからです。
鍼灸は、副交感神経を優位にし、リラックス効果を高める ことで、症状の緩和をサポートします。
🔹 リラックス効果のポイント
✅ ストレスを軽減し、神経の緊張をほぐす
✅ 睡眠の質を向上させ、疲労回復を促す
✅ ホルモンバランスを整え、神経の興奮を抑える
鍼灸は、神経の興奮を抑え、血流を改善し、筋肉の緊張を和らげることで、顔面痙攣の症状を緩和する効果が期待できます。特に、ストレスや疲労による悪化を防ぎ、自然な回復力を高めることができるのが大きなメリットです。
🔹 鍼灸の効果まとめ
✅ 神経の興奮を抑え、異常な痙攣を軽減
✅ 血流を改善し、神経や筋肉の回復を促す
✅ ストレスを和らげ、自律神経のバランスを整える
「薬に頼りたくない」「副作用のない方法で改善したい」とお考えの方に、鍼灸はとても有効な選択肢となります。