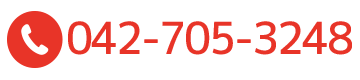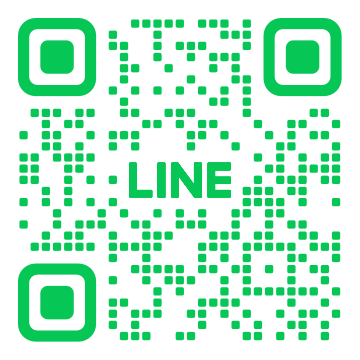「なんとなく冷える」を放っておかないで
朝晩の気温が下がり始める11月。「足先が冷たい」「手がかじかむ」「体がなかなか温まらない」――そんな冷えのサインを感じていませんか?冬本番を快適に過ごすためには、今の時期からの冷え対策がとても大切です。ここでは、冷えが起こる原因と、鍼灸的な視点からの体づくりのポイントをご紹介します。
なぜ冷えが起こるのか?
現代人の冷えは、単に気温のせいだけではありません。
エアコン・ストレス・運動不足・食生活の乱れなど、生活環境が体の「熱をつくる力」を弱めてしまっています。
特に女性に多いのが、「隠れ冷え」。
手足だけでなく、内臓が冷えているために、
・疲れやすい
・肩こりや頭痛が出やすい
・生理痛が重い
といった症状を引き起こすこともあります。
東洋医学でみる“冷え”の正体
東洋医学では、冷えは「気・血・水(き・けつ・すい)」の巡りが悪くなった状態と考えます。
•気の不足(気虚):エネルギーが足りず、体を温める力が弱い
•血の滞り(瘀血):血流が悪く、手足が冷える
•水の滞り(痰湿):余分な水分が体を冷やす
鍼灸では、これらのバランスを整え、体の内側から温まる体質づくりをサポートします。
日常でできる冷え対策
1.朝食で“温めスイッチ”を入れる
朝食を抜くと、代謝が上がらず1日中冷えやすくなります。
スープ・味噌汁・お粥などの温かいものを取り入れましょう。
2.湯船につかる習慣を
シャワーだけでは体の芯まで温まりません。
38〜40℃のお湯に10~15分、ゆっくり浸かるのがおすすめです。
3.「首」「手首」「足首」を冷やさない
この3つの“首”には太い血管が通っており、冷え対策の要です。
外出時はスカーフ・レッグウォーマーなどでしっかりガードを。
4.軽い運動で血流を促す
ウォーキングやストレッチ、階段の上り下りなど、
日常に“ちょっと動く”時間を意識的に増やしましょう。
鍼灸でできる「温め体質」づくり
鍼灸では、冷えに関係するツボ(例:関元・三陰交・足三里など)を刺激し、体のエネルギー(気)と血の流れを活性化させます。
また、自律神経の働きを整えることで、体温調節機能もスムーズに。継続的なケアで、冷えに負けない体質をつくることができます。