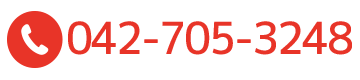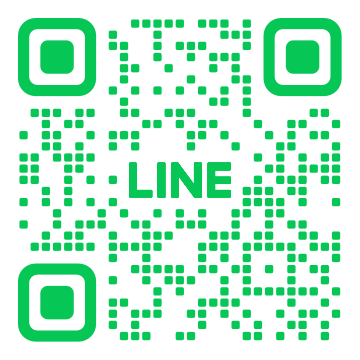五月病ってなに?
新年度が始まり、環境が大きく変わる春。
4月は新しい出会いや期待に胸をふくらませる時期です。しかし新しい環境で、緊張や疲れがピークになるのがこの時期です。
張りつめてきた糸がゴールデンウィークで、ぶっちりと切れて、ゴールデンウィーク明け頃から、会社や学校に行きたくない、なんだか気分が優れない、ぼんやりで不安、なんとなく元気が出ない……そんな不調を感じたことはありませんか?
もしかすると、それは「五月病」かもしれません。
五月病とは?
「五月病」は正式な医学用語ではありませんが、4月から新生活を始めた人が、5月頃に心身の不調を感じることを指す通称です。
新入社員や新入生だけでなく、転勤や異動、引っ越しなどで生活環境が変わった方にも起こることがあります。
主な原因
五月病の原因は主に**「ストレス」と「環境の変化」**にあります。
•新しい人間関係や仕事への適応のプレッシャー
•慣れない生活リズムや通勤・通学
•ゴールデンウィークで一時的に緊張がゆるみ、反動で気分が落ち込む
こうした心と体への負担が積み重なることで、自律神経のバランスが乱れ、不調が現れやすくなるのです。
どんな症状が出るの?
五月病では、以下のような症状がみられることがあります。
•朝起きるのがつらい
•食欲がない、または食べすぎる
•寝つきが悪い、眠りが浅い
•集中力が続かない
•気分が落ち込む、イライラする
•「何をしても楽しくない」と感じる
これらの症状が続くと、うつ病や適応障害に進行する可能性もあるため、軽く考えずに早めの対処が大切です。
こんな方は要注意
五月病は、誰でもかかる可能性があります。なかでも、受験や就職などの大きな目標を達成したことで、燃え尽き症候群(バーンアウト)のような状態に陥っている人や、環境が大きく変わったことで周りにうまくなじめないという人は、ストレスをため込みやすいので注意が必要です。
また、五月病の原因とされる適応障害やうつ病といった病気になりやすいタイプの人もいます。このような人は、性格的に几帳面でまじめ、責任感があるといった特徴があり、一人で抱え込んですべてをきちんとしようとします。気負いすぎずに、周りの人に協力を求めるようにしましょう。
日常生活で気をつけたいこと
五月病を予防・改善するために、以下のようなことを意識してみましょう。
1. 生活リズムを整える
毎日決まった時間に寝て、起きる。朝日を浴びて体内時計をリセットするだけでも、自律神経が整いやすくなります。
2. バランスのよい食事をとる
特にビタミンB群やたんぱく質は、神経の働きをサポートします。栄養が偏ると、心の不調にもつながります。
3. 軽い運動を習慣にする
散歩やストレッチなど、無理のない範囲で体を動かすことで、気分転換やストレス発散につながります。
4. 一人で抱え込まない
信頼できる人に話すだけでも、心が軽くなることがあります。会社や学校の相談窓口を活用するのも一つの方法です。
5. 休むことも“前向きな選択”
「頑張らないと」と無理をしすぎるのは逆効果。時にはしっかり休むことが、回復の第一歩になります。
-おわりに-
誰にでも起こり得る五月病。大切なのは、「気のせい」と思わず、自分の心と体の声にしっかり耳を傾けることです。
もし不調が長引いたり、日常生活に支障が出てきたと感じたら、早めに医療機関へ相談することをおすすめします。
新しい季節を、健やかに過ごすために。小さな不調も見逃さず、大切にしていきましょう!!